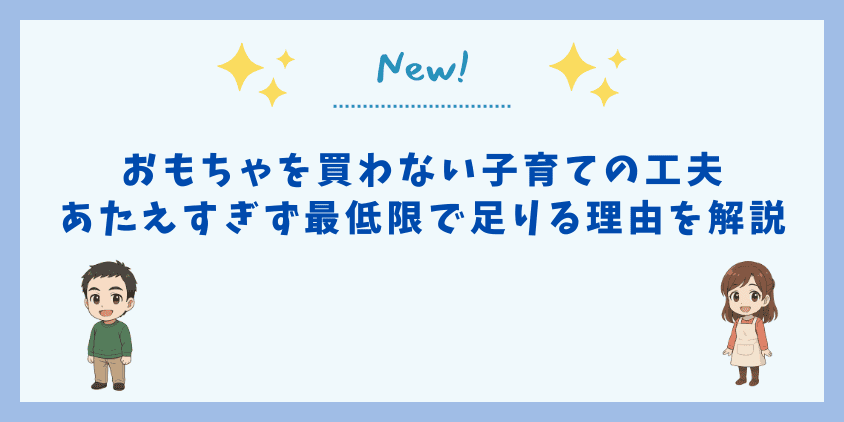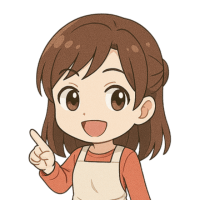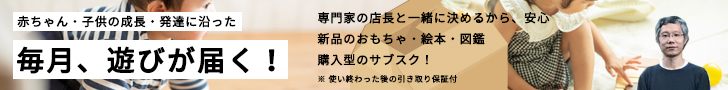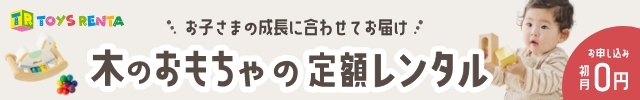おもちゃを買わない子育てって実際はどんな感じ?
おもちゃがなくても本当に子どもは満足できるの?
このような疑問を抱いていませんか?
おもちゃの種類や数が充実している現代では、次々と買いあたえてしまい部屋が散らかったり、すぐに飽きられたりして悩む親御さんも多いでしょう。
私自身も3人の子育てを通して、おもちゃを買いすぎた反省から「本当に必要なものは何か」を見直すようになりました。



この記事では「おもちゃを買わない子育て」の考え方から、欲しがるときの対応や手作り・自然遊びの工夫まで、体験を交えて紹介します。
「おもちゃを買わない」とは、最低限のおもちゃに絞って親子の関わりを大切にする子育てのスタイルです。
この記事を読めば、お金をかけずに子どもの想像力を育む方法がわかり、安心して子育てを楽しめるようになるでしょう。
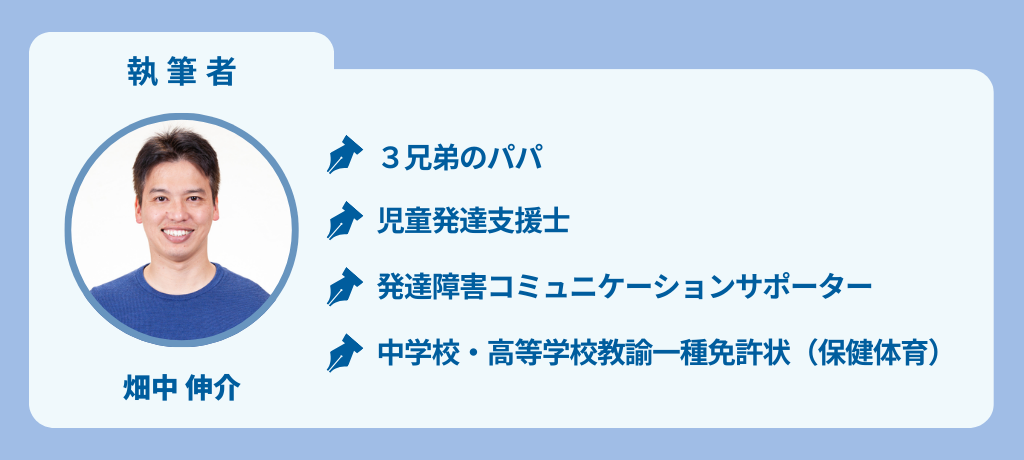
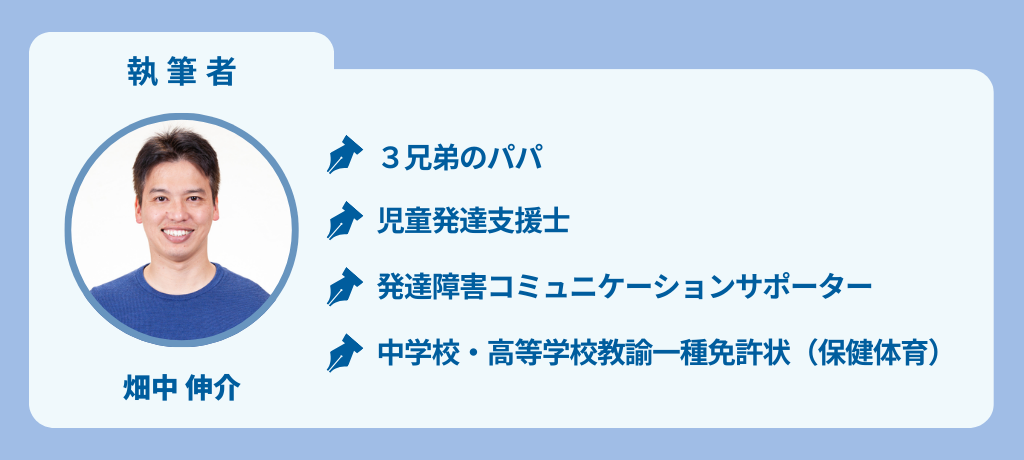
おもちゃを買わない子育ては「必要なものだけをあたえる」という考え方
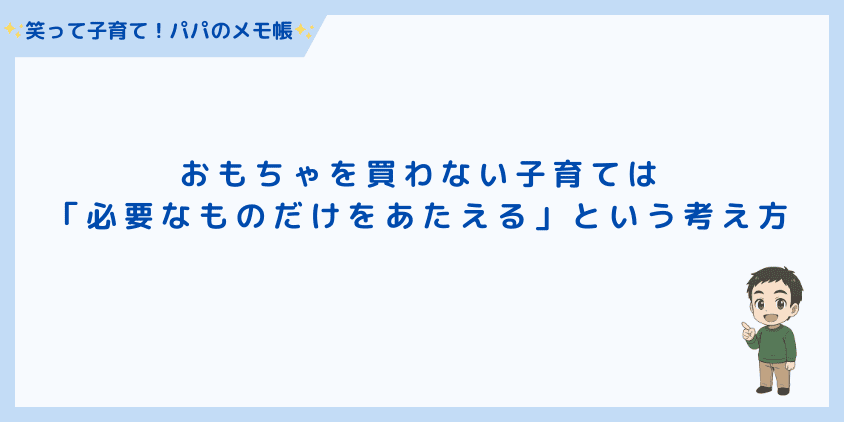
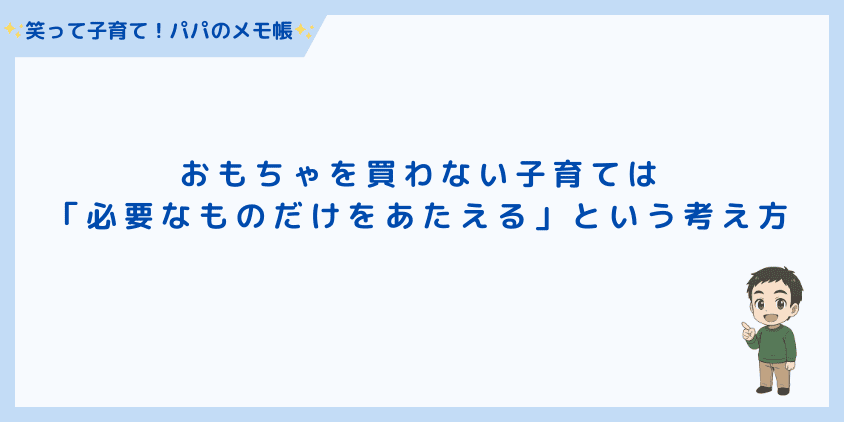
「おもちゃを買わない子育て」という言葉を聞くと、まったくおもちゃをあたえない厳格な子育て方法を想像するかもしれません。
実際は、子どもの成長に必要な最低限のおもちゃに絞ってあたえる、バランスの取れた子育て法です。
大切なのは「おもちゃを減らすこと」ではなく、子どもにとって本当に必要なものを選ぶ視点です。
おもちゃを買わない子育てを実践するには、以下のような工夫がおすすめです。
- 子どもが欲しがるたびにおもちゃを買わないようにする
- 誕生日やクリスマスなど特別な機会に厳選してあたえる
- 既存のおもちゃを組み合わせて新しい遊び方を見つける習慣をつける
「おもちゃを買わない」子育て法の目的は、限られたおもちゃで遊ぶことで、子どもの創造力や工夫する力を自然に伸ばすのが狙いです。
遊びを工夫したりおもちゃを手作りしたりすれば、子どもの想像力が高まります。
ただし、各家庭の価値観や環境に合わせて柔軟に取り入れることが大切で、完璧に徹底する必要はありません。
たとえば、家庭の状況に応じて以下のような工夫が考えられます。
- 共働き家庭:短時間で親子一緒に楽しめるシンプルなおもちゃを選ぶ
- 自然豊かな地域の家庭:外遊びを中心にして、おもちゃは最小限にする
- 兄弟が多い家庭:おもちゃを共有しながら、数をしぼる
それぞれの家庭環境に合った方法を取り入れると、無理なく「おもちゃを買わない子育て」を実践できます。
家族にとって無理のない範囲で実践し、子どもの成長を見守りながらバランスを調整していけばよいでしょう。
子どもがおもちゃを欲しがるときの対応
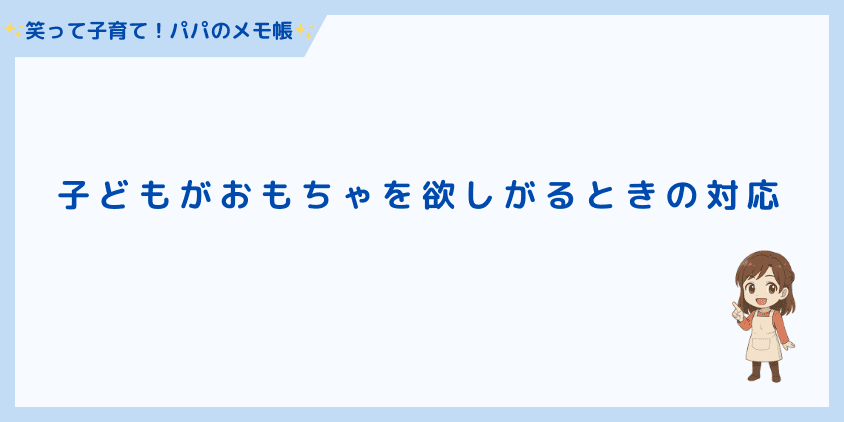
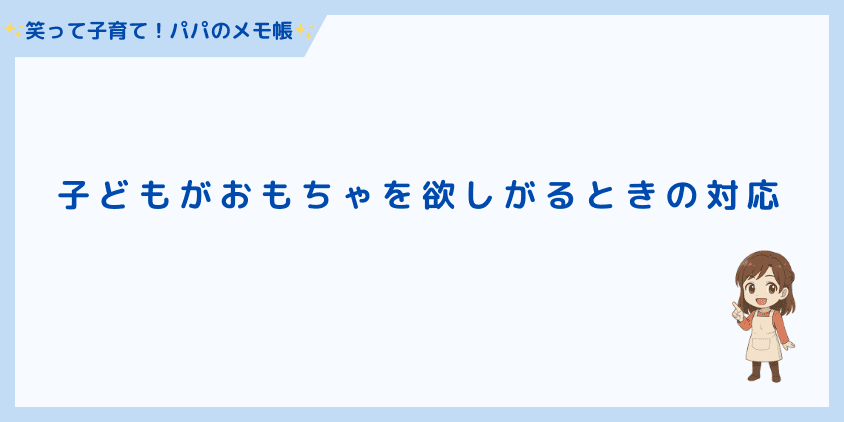
子どもが「おもちゃ欲しい!」と駄々をこねる場面は、多くの親が経験する日常的な出来事です。
駄々をこねる場面での親の対応は、子どもが我慢することを学んだり、感情をコントロールする力を身につけたりする貴重な機会となります。
子どもがおもちゃを欲しがるときに必要な対応は以下のとおりです。
- 気持ちを受け止めて声かけをする
- 買わない理由を優しく説明する
対応の仕方ひとつで、子どもは安心感を得ながら学びを深めていきます。
どのように声をかければよいのかを見ていきましょう。
気持ちを受け止めて声かけをする
子どもが「おもちゃが欲しい!」と言ったときは、まず気持ちを受け止めてあげましょう。
欲しいという感情自体は自然なもので、否定する必要はありません。
このおもちゃ欲しい!
そうなんだね。かっこいいもんね!
共感の言葉を返すと、子どもは自分の気持ちを理解してもらえたと感じて、落ち着きを取り戻しやすくなります。
たとえ泣いてしまっても「気持ちはよくわかるよ」と伝え続ければ、子どもは安心感を得られるのです。
一方で否定的な言葉には気をつけましょう。
パパ!これ買って欲しい
家に同じようなものあるからいらないよ!
欲しい気持ちを否定され続けると、自分を否定されたと感じて欲しいものがわからなくなります。
頭ごなしに否定するのではなく、子どもの立場に立って共感の姿勢を心がけましょう。
買わない理由を優しく説明する
気持ちを受け止めた後は「今日は買わないよ」と理由を子どもにわかりやすい言葉で説明しましょう。
否定するのではなく、子どもが受け止めやすい言葉で具体的に伝えることが大切です。
このおもちゃ欲しいなー!
今日は食材だけを買う日だから、お金が足りないの
理由を簡潔に伝えると、子どもは納得しやすくなります。
さらに前向きな約束を加えると効果的です。
また今度一緒に選ぼうね
お誕生日のときに買おうか
ただ我慢させるのではなく、状況に応じたタイミングを知らせてあげましょう。
感情的になって「絶対にダメ!」と強く否定するのではなく、穏やかな口調で一貫した態度を保ちましょう。
親の穏やかな説明を通して、子どもは我慢する力を少しずつ身につけていきます。
おもちゃを買いすぎると起きる3つの問題点
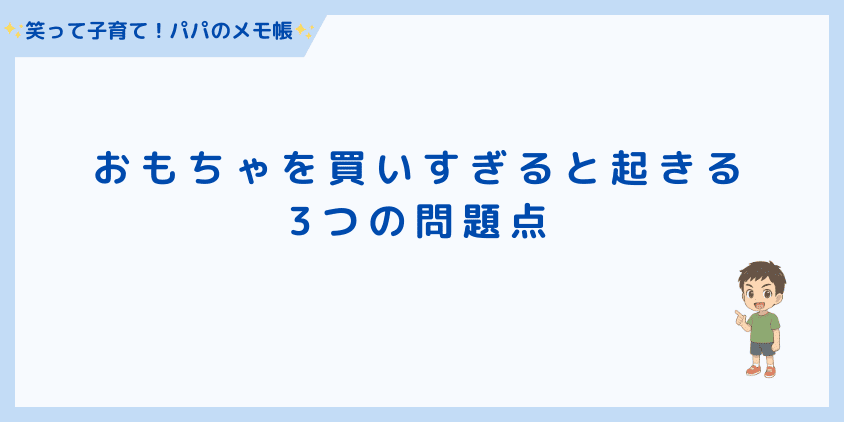
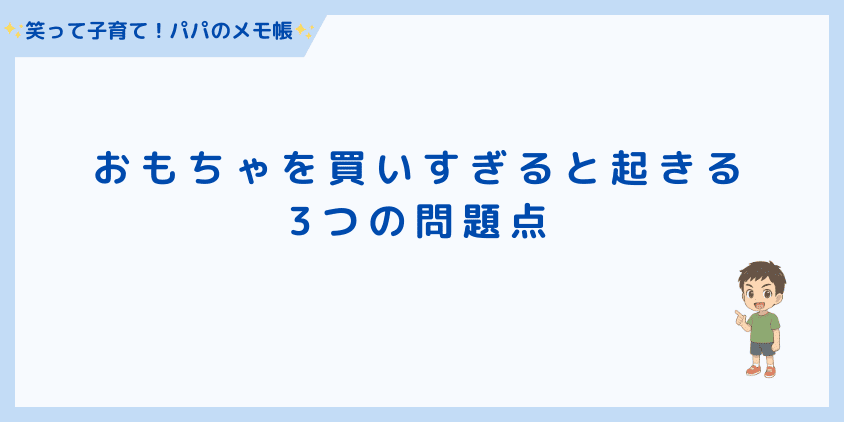
おもちゃの買いすぎは、子どもを喜ばせるよいことのように思えますが、実はさまざまな問題を引き起こします。
主な問題点は以下の3つです。
順番に見ていきましょう。
1. おもちゃが多いと集中力が続かない・すぐ飽きる
おもちゃの数が多いと、子どもは選択肢が多すぎて1つの遊びに深く取り組めなくなる場合があります。
目の前にあるおもちゃに次々と目移りして、浅い遊びを繰り返すようになるのです。
アメリカの研究でも、少ないおもちゃで遊ぶ子どもの方が長時間集中して遊べることが確認されています。
おもちゃが多すぎると、子どもは「もっと面白いものがあるかも」と考えて、すぐに次の遊びに移るクセがついてしまいます。



私も長男には「初めての子どもだから」と、一番おもちゃを買いあたえてしまいました。
幼い頃を思い出すと、次男や三男に比べて集中して遊ぶのが苦手で、1人遊びがうまくできなかった印象があります。
数が多いと1つのおもちゃでじっくり遊んだり、創意工夫して新しい遊び方を見つけたりする機会が失われてしまうのです。
子どもの想像力や探究心を養うチャンスが減ってしまうため、買いすぎには注意が必要です。
参照:乳児の行動と発達|環境中のおもちゃの数が幼児の遊びにあたえる影響
2. 増えすぎたおもちゃで収納や片付けに困る
おもちゃが増えすぎると収納や片付けで、以下のような問題も発生します。
- 片付けの手間が増え、親子ともにストレスになる
- 散らかるおもちゃでちょっとした負担になる
- 不要なおもちゃの管理や処分に悩む
収納場所が不足すると、適切な片付け場所がないため常におもちゃが散らかった状態になります。
リビングや子ども部屋におもちゃが散乱していると、掃除の負担が大幅に増え、家事をこなす親のイライラが募りがちです。
床に散らかったおもちゃは移動のじゃまになり、踏んでケガをする原因にもなります。
子どもの成長で使わなくなったおもちゃは、思い出で捨てられず、売るのも手間なため処分に困る家庭が少なくありません。
3. あたえすぎると「もっと欲しい!」につながる
おもちゃのあたえすぎは、子どもの心理面に影響を及ぼす可能性があります。
考えられる影響は、以下のとおりです。
- 「買ってもらえるのが当たり前」になる
- 我慢やものを大切にする気持ちが育ちにくくなる
- すぐ飽きて次を欲しがる消費グセにつながる
おもちゃを頻繁にあたえると「買ってもらえるのが当たり前」と考え、我慢やものを大切にする心が育ちにくくなります。
また、1つのおもちゃに飽きると「ほかのものが欲しい」と思いやすくなる場合もあります。
あたえることが習慣化してしまうと、大人になったときにも欲求をコントロールしにくくなるでしょう。
おもちゃのあたえ方を見直せば、子どもが我慢や感謝の気持ちを学び、豊かな心を育んでいけるでしょう。
おもちゃを買わない子育てで得られる4つのメリット
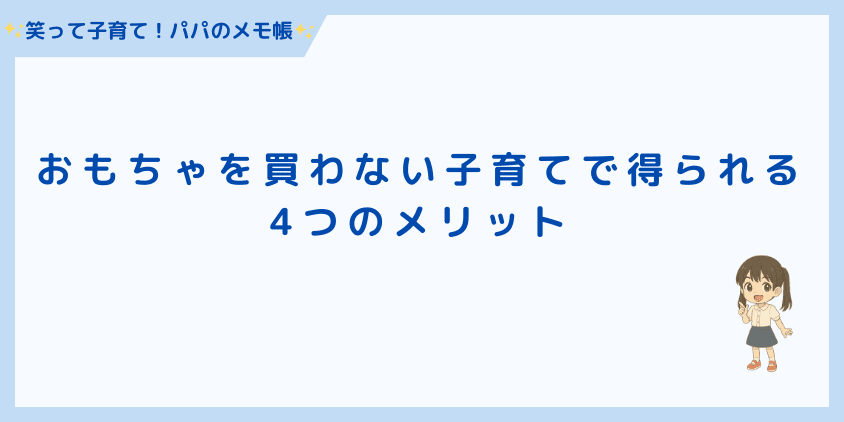
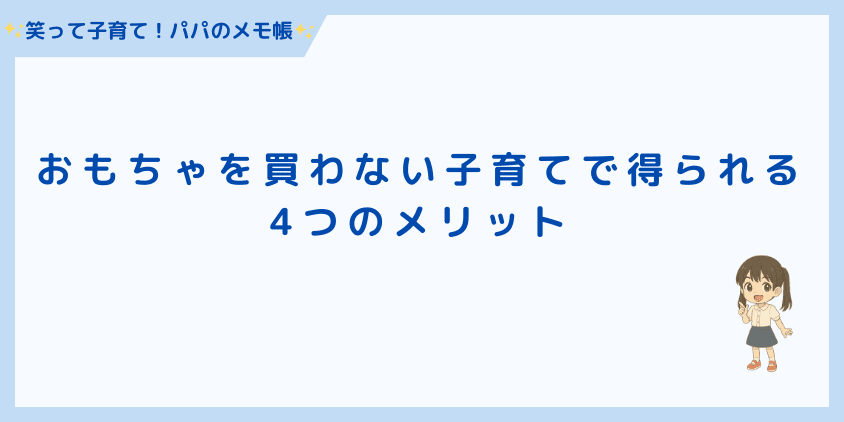
おもちゃを必要最小限に抑えると、多くのメリットが生まれます。
メリットは以下の4つです。
順番に確認してみましょう。
1. 身近なもので遊びを生み出すことで想像力が育つ
おもちゃを買わない代わりに、身近なものを使ってものを作ると、子どもの想像力が育てられます。
身近なものの代表例は、以下のとおりです。
- 牛乳パック
- トイレットペーパーの芯
- ペットボトル
- 段ボール
決められた遊び方がないからこそ、自分で考える力が自然に育つのです。
タイヤは何を使ったらいいかな?
そうだ!ペットボトルのふたを使ったらいいんじゃない?
牛乳パックを使って長男と次男が工作をしているときの会話です。



作ったあとは、長男が車掌さん、次男が電車を動かし電車ごっこをしていました。
身近なもので遊んだ後は、不要になったらゴミとして気軽に処分できるのも大きなメリットです。
思い出に縛られることなく、新しいアイデアに挑戦する気持ちも育まれるでしょう。
2. 手作りや一緒の遊びで親子のコミュニケーションが増える
おもちゃが少ない環境では、親子で一緒に遊びを作り上げる時間が自然と増えていきます。
今日はお家を作ってみたい!
どうやったら作れるかなー?
一緒に遊びを工夫する過程そのものが、親子にとって大切な思い出になります。
子どもにとって親との時間は何よりも貴重で、一緒に過ごす時間が多いほど安心感や愛情を感じられるでしょう。
遊びで得られるコミュニケーションは、既製品のおもちゃでは味わえない特別な体験となり、親子の絆を深める大切な時間です。
3. おもちゃが少ないから部屋が散らからず快適に過ごせる
おもちゃの数が限られていると、管理が楽になり、片付けも短時間で済むようになります。
子どもも自分のおもちゃがどこにあるかを把握しやすく、遊んだ後の片付けを自分でできるようになるでしょう。
リビングや子ども部屋におもちゃが散乱せず、歩いているときにおもちゃを踏んでケガをする心配もありません。
小さくて硬いおもちゃを踏んでしまうと、非常に痛いので注意してください。
親にとってもストレスが大幅に軽減され、家族全員が快適に過ごせる環境が整います。
また、少ないおもちゃを大切に使う習慣が身につくため、ものを丁寧に扱う心も育まれます。
「今あるもので工夫して遊ぶ」という姿勢が、子どもの創意工夫する力にもつながるのです。
4. おもちゃ代を抑えて生活費に余裕が生まれる
おもちゃの購入を控えると、家計の不要な出費を削減できます。
おもちゃはつい衝動的に買ってしまいがちですが、子どもがすぐ飽きてしまうケースも多く、結果的に無駄な支出につながりやすいです。
浮いた分を習い事や教育費、家族での外出や体験活動に回せば、子どもの成長にもプラスになります。
家計に余裕が生まれると親の心にもゆとりができ、経済的なストレスが減るのも大きなメリットです。
「無駄遣いをしてしまった」と罪悪感を抱かずに済み、安心して計画的な家計管理ができるようになるでしょう。
おもちゃはどれくらい必要?年齢別の目安
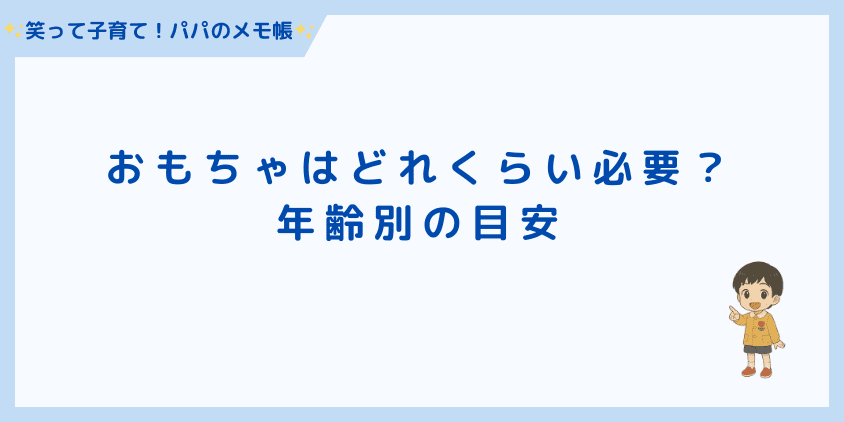
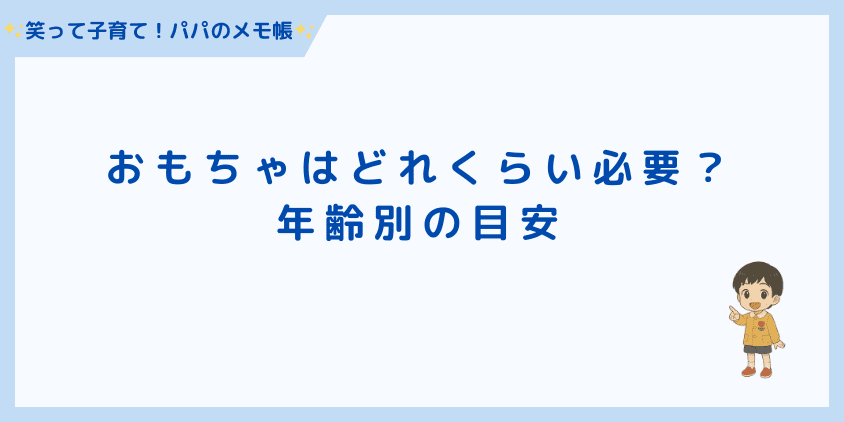
子どもの成長段階に応じて、必要なおもちゃの種類や数は大きく変わります。
各年齢で適切な刺激をあたえるために、おもちゃがどれくらい必要か以下の年齢別の目安を紹介します。
年齢ごとにどのようなおもちゃが適しているのか、確認していきましょう。
新生児〜0歳はおもちゃ不要!親の声や抱っこが一番の刺激
新生児期の赤ちゃんにとって重要なのは、おもちゃではなく親からの「声かけ」と「抱っこ」です。
赤ちゃんは、親の柔らかい声や豊かな表情を通して心が落ち着き、脳の発達にもつながります。
おもちゃではなく、以下のような行動が赤ちゃんにとって知育となります。
- 「おはよう」「気持ちいいね」などの日常的な語りかけ
- 授乳時のアイコンタクト
- 抱っこでのスキンシップ
おもちゃを用意するなら、ガラガラや柔らかい布おもちゃを1~2個程度で十分でしょう。
また、新生児の匂いは特有の優しくて甘い香りがするため、抱っこしているだけで幸せな気持ちになります。



新生児〜0歳だからこそ味わえる瞬間なので、ぜひ大切にしてください。
新生児期は親子の触れ合いが何よりの刺激となり、赤ちゃんの健やかな成長につながります。
赤ちゃんの反応を見ながら、自然な関わりを大切にしていきましょう。
1歳は積み木や布絵本など「最低限のおもちゃ」で十分
成長の速度にもよりますが、1歳頃になると手や指の動きが発達し、ものを掴んだり放したりできるようになります。
1歳児には以下のようなおもちゃがおすすめです。
- 積み木
- 布絵本
- 簡単な型はめパズル
複雑なものよりも、手を使う練習になる基本的なおもちゃがあるとよいでしょう。
また、身近な日用品でも十分に遊べる時期でもあります。
段ボールでトンネルや段差を利用しすべり台を作るなど、工夫次第で無限の遊びが生まれます。



私の三男もお兄ちゃんが作った短いすべり台を、嬉しそうに滑っていました。
大量のおもちゃより、良質なおもちゃを少数選び、遊びを深めることが成長につながります。
2〜3歳はごっこ遊びや積み木で想像力を広げる時期
2〜3歳は模倣遊びやごっこ遊びが盛んになる時期で、周囲の大人や兄弟の行動を真似したがるようになります。
2〜3歳には以下のような、発展性のある少数のおもちゃが非常に有効です。
- 人形
- ままごとセット
- 積み木
1つのおもちゃからさまざまな遊び方を生み出せる、組み合わせ型のおもちゃを活用すると、子どもの想像力は大きく広がります。
たとえば、積み木は家や車、お城にも変身するため、創造性を存分に発揮できるでしょう。
想像力を広げるために大切なのは、おもちゃの数ではなく遊びの多様性です。
シンプルなおもちゃほど子どもの発想力を刺激し「自分で考えて遊ぶ力」を育てられます。
親も一緒に遊びながら、子どもの創造力を肯定してあげることが成長につながります。
4歳以降はルール性のあるおもちゃを少数取り入れる
4歳以降になると、簡単なルールを理解できるようになり、社会性や協調性を学ぶ段階に入ります。
以下のようなルール性のある遊びを取り入れるとよいでしょう。
- ボードゲーム
- カードゲーム
- すごろく
友達や家族と遊ぶことで順番を待つ、負けても泣かない、相手を思いやるなどの社会性が自然に育まれます。
「勝った喜び」や「負けた悔しさ」を経験すれば、感情のコントロールも学べるでしょう。
4歳以降でも多くのおもちゃは必要ありません。
家族で楽しめるゲームを取り入れると、親子のコミュニケーションも豊かにしてくれます。
おもちゃを買わないで取り組む子育ての方法5つ
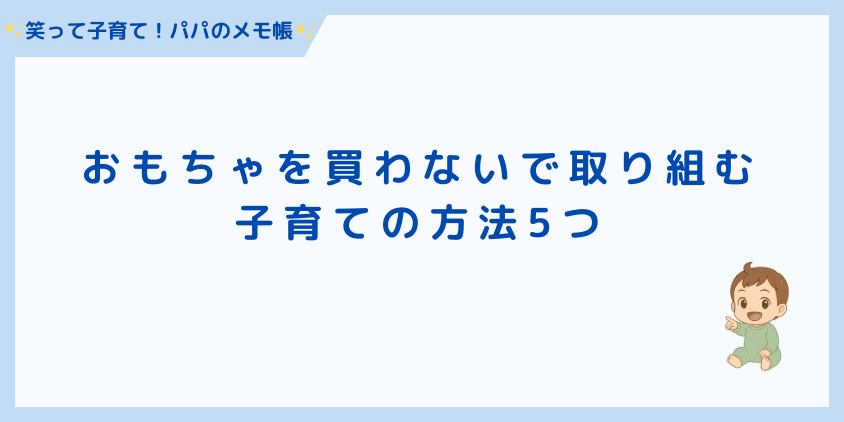
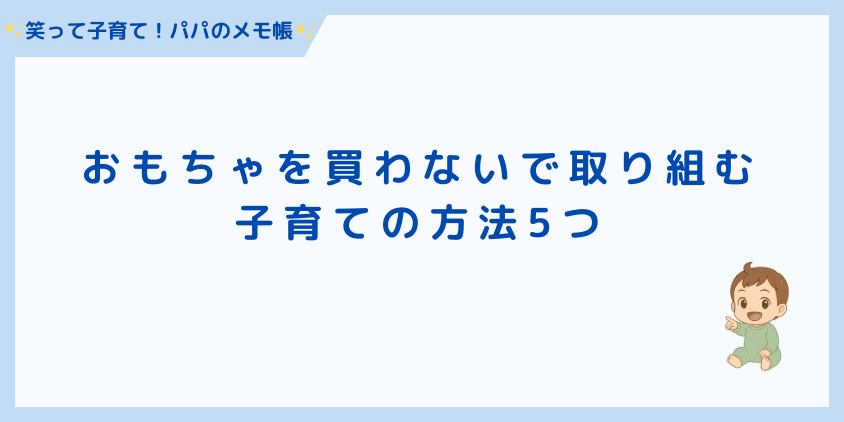
おもちゃを買わない子育てを実践するための方法は以下の5つです。
身近な工夫から地域のサービスまで、子どもの成長を支える方法を確認しましょう。
1. 牛乳パックや段ボールでおもちゃを手作りする
牛乳パックや段ボールなどの身近な材料を使えば、安全で楽しいおもちゃを簡単に手作りできます。
材料費はほとんどかからず、ハサミやテープといった基本的な道具があれば十分です。
息子たちと牛乳パックを使って作成した車のおもちゃがこちらです。


牛乳パックを車のボディ、タイヤはペットボトルのふたを利用しています。
周りに紙を覆ってあげると、子どもが好きな絵を描くことも可能です。


作る過程で子ども自身がハサミの使い方や組み立て方を学べるため、完成品で遊ぶ以上に教育的価値があります。
何より、子どもが「自分で作った」という達成感を味わえるのがメリットです。
市販のおもちゃでは得られない、創造する喜びと工夫する力が自然に身につくでしょう。
2. 公園や自然遊びで五感と体力を育てる
公園や河原、森林など、身近な自然環境が子どもにとって最高の遊び場です。
自然を活用した以下のような遊びは五感を刺激し、体力づくりにも効果的です。
- 虫取り
- 砂遊び
- 草花集め
とくにパパにとって、虫取りは子どもの頃の思い出を呼び起こす特別な体験かもしれません。
カブトムシやクワガタを探した記憶がよみがえり、子どもと一緒に夢中になって虫を追いかける時間は、親子の絆を深める貴重な機会となるでしょう。



私の息子も虫や生き物を取るのが大好きで、一緒に夢中になって楽しんでいます。
子どもが捕まえた「カナヘビ」を育て始めて1年ほどになりますが、今では卵の孵化にも成功し、赤ちゃんを育てています。


今ではカナヘビ5匹の父親としても奮闘中です。
餌も食べてくれるようになりました。


子どもとお世話をする時間も今ではかけがえのない時間です。
自然に触れながら過ごす時間は、子どもの五感や体力を伸ばすだけでなく、家族の笑顔を増やすきっかけになるでしょう。
3. 支援センターや児童館を活用して多様なおもちゃに触れる
地域の子育て支援センターや児童館は、無料で利用できる施設が多く、家庭では用意できない大型おもちゃや知育教材の体験が可能です。
支援センターや児童館では、以下のようなおもちゃで自由に遊べます。
- すべり台
- ボールプール
- 積み木セット
施設では他の親子とも自然に交流でき、子どもにとって社会性を育む貴重な場となります。
同年代の子どもたちと一緒に遊べば、協調性や思いやりの心も自然と身につくでしょう。
施設によっては読み聞かせ会や工作教室なども開催されており、さまざまな学びの機会に参加できます。
家にいるだけでは得られない多様な刺激を、費用をかけずに子どもに体験させられます。
絵本や読み聞かせで想像力を広げる
絵本には、おもちゃでは得られない知的刺激をあたえ、以下のような効果があるといわれています。
- 新しい言葉や表現に触れることで語彙力が育つ
- 登場人物の気持ちを想像することで感情表現が豊かになる
- 物語の世界に入り込む体験から想像力が大きく広がる
親子で過ごす読み聞かせの時間は、愛情を深める大切な習慣となるでしょう。
物語絵本から図鑑まで、本は幅広い知識と感性を育てられます。
絵本選びをサポートしてほしい方は、「いろや商店くらぶ」のようにおすすめの本を届けてくれるサービスを試してみてください。
子どもの成長にぴったりな絵本が定期的に届き、親子の時間を充実させてくれるでしょう。
おもちゃレンタルサービスで必要なときだけ利用する
おもちゃレンタルサービスなら、月額でさまざまな知育玩具を利用でき、子どもの成長に合わせて定期的に交換可能です。
購入するよりもコストパフォーマンスがよく、不要になったおもちゃが家に溜まってしまう心配もありません。
年齢や発達段階に応じた最適なおもちゃを専門家が選定してくれるサービスも多く、親がおもちゃ選びに悩む必要がなくなります。
子どもが飽きた頃に新しいおもちゃと交換できるため、常に新鮮な刺激をあたえ続けられますね。
以下では、おすすめのおもちゃレンタルサービスを3つご紹介します。
それぞれ特色が異なるため、お子さんの年齢や家庭の方針に合わせて選んでみてください。
Cha Cha Cha(チャチャチャ)|適齢に合わせた知育玩具
Cha Cha Chaは月齢や興味に合わせて定期的におもちゃを届けてくれるサブスクサービスです。
親の悩みを減らしながら子どもの成長をサポートできます。
Cha Cha Cha(チャチャチャ)
- 月額料金は3,910円で定価17,000円相当のおもちゃが6~7点届く
- 2か月ごとに新しいおもちゃと交換できる
- おもちゃカタログから好きなものをリクエストできる
- 破損時の弁償が不要で安心して利用できる
Cha Cha Cha(チャチャチャ)
Cha Cha Cha(チャチャチャ)を
おもちゃのサブスク「chachacha」頼んでみたからレポ🧸🎈
— のんぴ☺︎🦕🩵 (@sakeyakuzaneko) September 3, 2025
結論!めっちゃいい!!!✨
◆ギャオス(0歳8ヶ月)の様子
ギャオスはくるくる回る系のおもちゃが好きで、事前にカウンセリングシートでその旨伝えてたからか、ドンピシャなおもちゃが届いた✨
興味津々で遊んでて楽しそう😄(動画)… pic.twitter.com/OpgypDr26S
初めておもちゃのサブスク頼んでみた😊
— ジャピーナのリコ🇹🇭WEBライター (@riko_kaigai) May 15, 2025
初月1円なのに初回から総額4万円分(Amazon調べ)のおもちゃ届いて驚いた🤣✨✨✨
リクエストしたアンパンマンのおもちゃも無事に届いたし、ムスッコもテンション上がってる🥳#おもちゃのサブスクchachacha pic.twitter.com/35csWtWCU6
口コミからもCha Cha Chaは、子どもの興味に合ったおもちゃが届き、破損時の弁償が不要でなので安心できるサービスです。
さらに初月は1円で試せるため、安心して始めやすいサービスといえるでしょう。
おもちゃのサブスク「チャチャチャ(ChaChaCha)」について詳しく知りたい方は以下の記事も合わせてご覧ください。
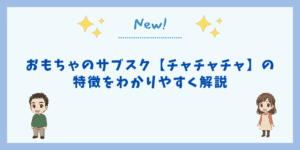
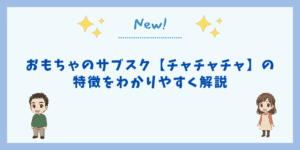
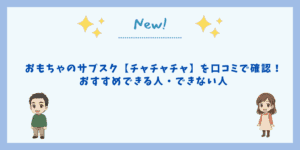
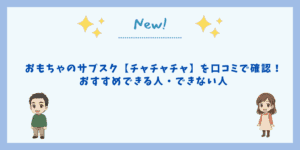
Circle Toys (サークルトイズ)|子供向け大型遊具レンタルのサブスク
Circle Toys(サークルトイズ)は、ジャングルジムやすべり台、トランポリンなどの大型遊具を月額でレンタルできるサブスクサービスです。
大型遊具は子どもに人気ですが、値段が高い・サイズが大きく置き場所に困るなどの理由で購入を迷う家庭は少なくありません。
Circle Toys(サークルトイズ)のメリットを確認しましょう。
- 高価な大型遊具が月額3,980円からの定額制で利用できる(送料無料プランあり)
- 本格的な大型遊具を交換しながら利用できる
- 大型遊具のラインナップが豊富である
- 使わなくなったら返却するだけで収納の心配がない
トランポリンや電動乗用車、ウォータースライダーまで、子どもが夢中になる遊具が豊富に揃っています。
Circle Toys(サークルトイズ)を利用した人の口コミを見てみましょう。
・コロナの影響で幼稚園が休園してしまい、おうち遊びで困っていました。 そこで大型遊具を借りてみたのですが、自宅で思いっきり体を動かして遊んでもらえて大変助かりました!
(20代 女性 主婦)・買ってみたい遊具があったのですが、折角購入して使わなかったら勿体ないと思っていたところ、 たまたまサークルトイズにあったので借りてみました。実際に試して購入前の参考にできたので良かったです!
(30代 女性 公務員)
引用元:Circle Toys(サークルトイズ)|ご利用者様の声
口コミから、Circle Toysは「自宅遊びの悩みを解消しつつ、購入前の試し利用にも最適な大型遊具レンタルサービス」だといえます。



私もトランポリンやすべり台を購入しましたが、サイズが大きく収納に困るためありがたいサービスです。
体を動かす遊びを重視したおもちゃを利用したい場合は、Circle Toys(サークルトイズ)を利用しましょう。
Circle Toys(サークルトイズ)のサービス内容や特徴について、詳しく知りたい方は以下の記事もあわせてご覧ください。


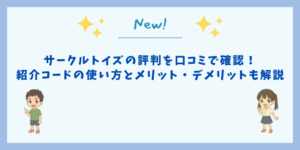
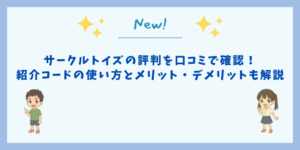
トイズレンタ|【初月無料】木のおもちゃサブスクプラン
トイズレンタは、高品質な木のおもちゃを定額でレンタルできるサブスクサービスです。
木のおもちゃは成長によいとわかっていても価格が高く、購入をためらう家庭は少なくありません。
「良質なおもちゃをあたえたいけれど高すぎる」と悩む方に、トイズレンタは手頃な料金で木のおもちゃを利用できる選択肢を提供しています。
トイズレンタをおすすめするポイントは以下のとおりです。
- 高品質な木のおもちゃを手頃な定額料金で利用できる
- 専門家が子どもの成長に合わせて厳選してくれる
- 初月無料で試せるので、体験してから継続を検討できる
専門家が子どもの成長に応じて選んだ木のおもちゃで、自然の温もりを感じながら想像力や生きる力を育てられます。
トイズレンタを利用した人の口コミを見てみましょう。
おもちゃのサブスク、トイズレンタ2回目のおもちゃが到着!
— えみりー3y (@citron_flan) August 13, 2022
ラインナップやサポートの親切さが気に入って継続。
毎回LINEで相談しながらおもちゃを決められるのがありがたい。
始まったばかりのサービスなので、今回も全部新品のように綺麗でした(新品かも)👏
早速夢中で遊んでる🥰 pic.twitter.com/9JCKrrTHHY
口コミから、トイズレンタは「デザイン性が高く質のよい木製玩具を、丁寧なサポートとともに提供してくれる信頼性の高いサービス」だといえます。
初月無料でお試しできるため、木のおもちゃのよさを体験してから継続の検討も可能です。
トイズレンタは質の高い知育環境を求める家庭にぴったりのサービスです。
おもちゃを買わない子育てについてよくある質問
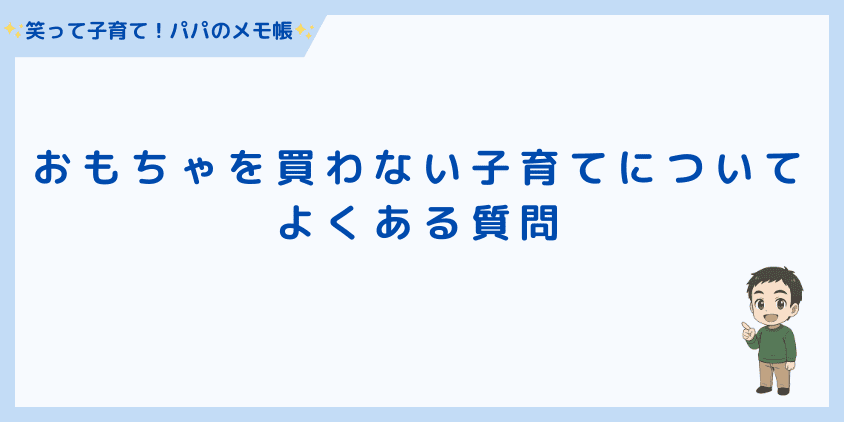
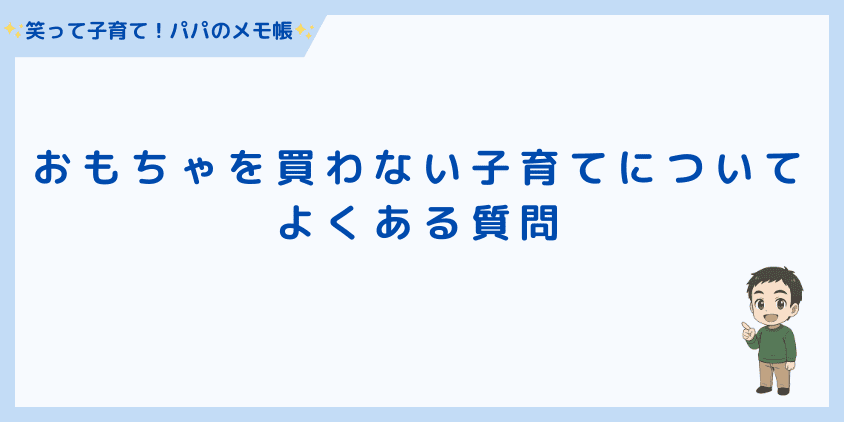
「おもちゃを買わない子育て」に関するよくある質問と回答をご紹介します。
子どもにおもちゃは本当に必要ですか?
子どもにとっておもちゃは必要ですが、大切なのは「数」より「質」であり、少なくても発達を十分に支えられます。
子どもの成長にとって大切なのは、多くのおもちゃに囲まれることではなく、想像力を育てる環境です。
シンプルな積み木や絵本、身近な材料を使った手作りおもちゃでも、子どもは豊かな遊びを生み出せます。
選択肢が多すぎると集中力が続かず、深く遊び込めなくなる場合もあるでしょう。
親子のコミュニケーションや自然体験など、おもちゃ以外の刺激も子どもの発達には欠かせません。
買わなくてよかったおもちゃは何ですか?
買わなくてよかったおもちゃは、以下のとおりです。
- 電池式で一瞬しか楽しめないもの
- 大きすぎて場所を取るもの
- 年齢が合わずすぐに遊ばなくなるもの
音や光が派手な電子おもちゃは最初こそ子どもの興味を引きますが、受動的な遊びになりがちで長続きしません。
また、大型の遊具は置き場所に困り、子どもが成長すると使わなくなって処分に悩むケースが多いです。
対象年齢を考えずに購入したおもちゃも、すぐに飽きられてしまう傾向があるので注意してください。
おもちゃ代は平均いくらですか?
家庭ごとにおもちゃ代には幅があり、年間の支出は5,000円未満から3万円程度が一般的です。
「誕生日やクリスマスだけ」といったルールを決めている家庭も少なくありません。
小学館の調査によると、年間1万円〜3万円という家庭が約半数を占め、次に5,000円〜1万円という結果でした。
最近では、おもちゃレンタルサービスを利用したり、フリマアプリで中古品を購入したりして、賢く節約している家庭も増えています。
特別な日だけに購入を限定すれば、子どももおもちゃへの喜びが増し、ものを大切にする心も育まれるでしょう。
おもちゃを買わない子育てで親子の時間を大切にしましょう
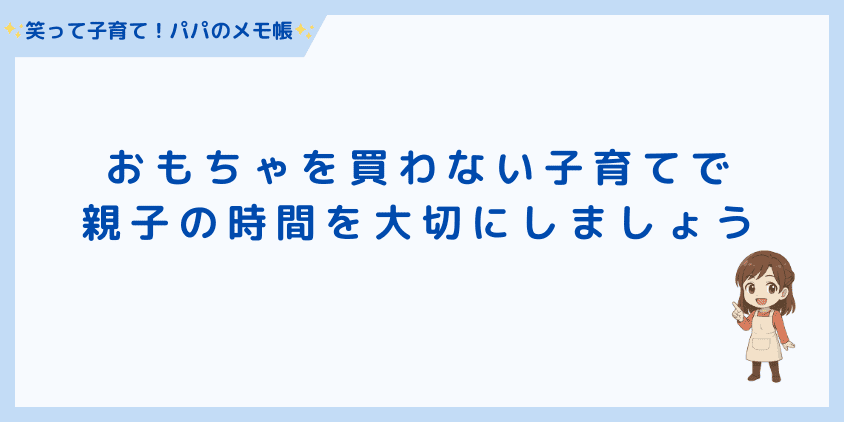
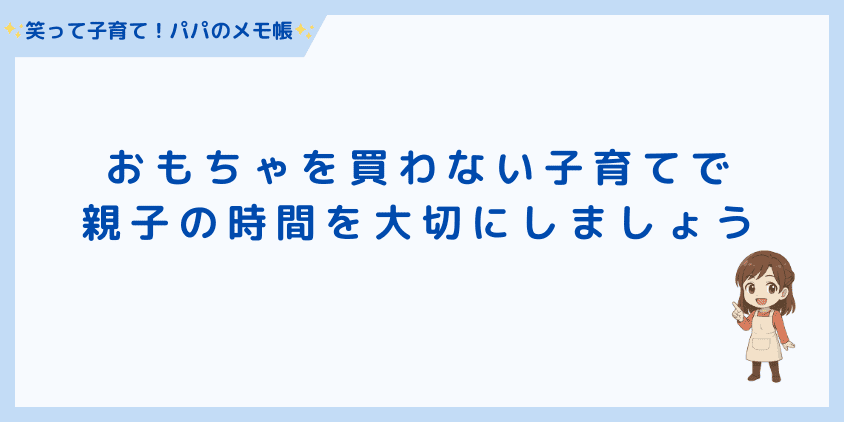
今回は「おもちゃを買わない子育て」について、工夫や実践方法をご紹介しました。
「買わない」という表現は、おもちゃを完全に排除する意味ではなく、最低限に抑えて子どもとの関わりを大切にする育て方です。
多くのおもちゃに囲まれるより、限られたもので工夫して遊ぶことで、子どもの想像力や創造性が自然と育まれます。
手作りおもちゃや自然遊び、読み聞かせなど、お金をかけなくても親子で楽しめる方法は多くあります。



大切なのはおもちゃの数ではなく、親子の関わりの深さです。
「おもちゃを買わない子育て」を取り入れて、親子の時間をもっと楽しみましょう。
子どもと一緒に工夫し、成長を見守りながら、かけがえのない日々を過ごしていってください。